役立たずのダムを取り壊せ
すべては川の自由のために。常識を覆した挑戦者たちのドキュメンタリー。
僕が2013参院選で主張した「破壊から再生の公共事業へ」を、
まさに地でいく動きが今、破壊のオオモトである米国で起きている。
日本の環境運動に(或いは社会に)、決定的に欠如している
「とんちとユーモア」をまざまざと見せつけられる。
あらゆる環境運動に関わっている人々に、
あるいは国の現状を憂いてそれを変革しようと小さな足掻きを営んでいる人々に、
必ず観てほしい映画である。
- 三宅洋平((仮)ALBATRUS/NAU代表)
今や諸悪の根源は、一人一人の小さな無責任。
今を生きる私達が気付き、動き出さなきゃならないんだ!
- 伊勢谷友介(俳優/映画監督/株式会社リバースプロジェクト代表)
各界著名人のおすすめメッセージはこちら!
http://damnationfilm.net/message/
News
- 2015/10/07
- 映画『ダムネーション』オンラインで配信開始!
- 2015/09/18
- ダムネーションの全国上映!(10月-11月)
- 2015/05/21
- 映画『ダムネーション』のDVDが発売に!
- 2015/05/12
- 今月5月、2劇場で映画『ダムネーション』公開!
- 2015/03/18
- 映画『ダムネーション』に52分バージョンが追加!
About the film
小さい頃、自分で散らかしたものは、自分で片付けるように教えられる。
それは私たちの“家”である地球に対しても言えるはずだ。
破壊的ですぐ役立たなくなるダムを建てたのなら、
それを片付け、自然を元通りにする責任が私たちにはあるはずだ。
- イヴォン・シュイナード(パタゴニア創業者、映画『ダムネーション』製作責任者)
アメリカにおいて「ダムを建設し増やしていくこと」が主流だった50年前から、
「ダムを撤去する」という選択肢へと移り変わってきた現代までを、
川の自由を求め続けてきた、さまざまな活動家に光を当てて追いかけます。
More info
破壊すべきダムがあるかぎり
“ダムバスター”は挑戦し続ける
アメリカ全土につくられた7万5千基のダム。それらの多くは、川を変貌させ、魚を絶滅させ、それにもかかわらず期待される発電・灌漑・洪水防止のいずれにおいても低い価値しか提供していない。むしろダムの維持には高い経済的コストもかかっている。そんな負の面ばかりのダムを「撤去」する選択が、アメリカでは現実になってきた。だが「ダム撤去」が当たり前に語られるようになるまでには、「クレイジー」と言われながも川の自由を求め続けてきた人びとの挑戦があった。彼らのエネルギーにより「爆破」が起こるドキュメンタリー。
自然の良さは人間が何もしなくてもいいこと。
ただそのままにしておけばいい。
地球の血管にも例えられる川。ダムが及ぼす影響は、私たち生き物すべてに及ぶ。ダムが撤去されたとき時、川は解放され、みずから元の姿に回復していく。本作品が映し出す川の生命力と美しさは、人間も自然の一部なのだということを改めて気づかせてくれる。そして、技術により自然を征服してきた過去と決別し、新しい未来をつくりだす希望の光を見せてくれる。製作責任者はパタゴニア創業者のイヴォン・シュイナード。共同プロデューサーは生態学者で水中写真家のマット・シュテッカー。
Data
| 原題 | DAMNATION | 製作年 | 2014 |
|---|---|---|---|
| 製作国 | アメリカ | 制作 | シュテッカー・エコロジカル&フェルト・ソウルメディア |
| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 87分、52分 |
Cast & Staff
| 監督 | ベン・ナイト&トラヴィス・ラメル | 製作総指揮 | |
|---|---|---|---|
| プロデューサー | ベーダ・カルフーン | 原作 | |
| 脚本 | 音楽 | ||
| 撮影 | 編集 | ベン・ナイト | |
| キャスト | |||
Review(4)
16/02/24 11:27
16/02/24 11:29
1997年アメリカのエドワードダムで始めて撤去命令が出たとのニュースを聞き、以後ダム撤去の情報を集めてまわったものだ。
2000年、ダムを電力会社から買い取って撤去するというペノブスコット川のニュースが届いたときは、その規模と進度に驚いたものだ。以後細々と次々とニュースは届けられてきたが、それでも届かなかった人たちへ、「ユーモア溢れる映画」という形でその情報が届くようになった。それがダムネーションだった。映像を通じ「あの巨大なダムでも撤去できるのだ」という驚きは確実に広がっているように思う。その驚きはライト兄弟が空を飛ぶ姿を見た時の「人は空を飛べるのだ」というブレイクスルーと似ている。
社会的に手法や技術が洗練されると撤去という選択肢がごく当たり前に選ばれるのだと思う。当然社会に必要とされているダムではなく、問題が多いダムから順次手が入るだろう。多くの事例をもとに、撤去に対するアイディアや手法が次々と生み出されている。
2011年に小樽の奥沢ダムがコストと安全性のためにさらりと用途廃止され、一部撤去された。驚くべきことに、たいして大きなニュースにならなかった。ダム撤去という手段が、センセーショナルなものではなく、改修やメンテナンスのようにごく当たり前の選択肢であって欲しいと願う。管理者がだれであれ、行政が撤去費用を支出するということもまた、問題を解決するために必要な形であり、仕組みは徐々に洗練されていくだろう。なにしろ日本にもまだまだ多くのダム撤去要望地がある。撤去するしないにかかわらず、撤去に関する議論が起きた土地に、この映画が広く届くことを願ってやまない。「撤去はありえないこと」として選択肢にすら入れられず、ただ問題の先送りと税金の無駄遣いとなる対策を選択してしまうのを防ぐことが出来るかもしれない。
2017年夏、私は荒瀬ダムが撤去され戻ってきた球磨川の流れを用いたラフティングやアユ釣り体験のツアーを行う会社を興した。今でも時々ツアーで川の流れの上にありながら、そこにあったあの巨大なコンクリートの塊を思い出し夢ではないかと思うことがある。ダム撤去で戻った流れで遊んだ後、お客様と共にダムネーションを見る。お客様の反応を見ながら、さらなる球磨川の未来を、日本の川の将来を想像する。5年後には、このレビューもまた時代遅れになっていて欲しい。
Reborn代表・リバーガイド 溝口隼平
https://www.facebook.com/rebornkumagawa/
上映者の声
映画上映とその後のトークの時間を設けたことで、映画の解説と問題提起につながり、参加者にとって、映画のメッセージの理解を深め、遠い海外のことではなく身近なものとして考える場になった。
熊本では、2020年の球磨川豪雨災害後に川辺川ダム計画が復活。流域住民や市民の間からは疑問の声が出ているが、国は一方的に進めつつある。そんな中で、人びとの暮らしと川はどう関わってきたか、ダム建設のためにすでに失われてきたもの、世界の潮流と日本の現状を考えたいと企画した。映画「ダムネーション」を入口として、身近なこと、未来のことを参加者と共に考えたいという主催者の意図に沿った上映会となった。
村の中央を流れる鎖川への関心と調査・体験について提案を行っています。活動へのカンパにより、これまでの住民の皆さんへの感謝を込めて無料上映となりました。
上映時に30人の方から一言ずつお話しいただき、元気をいただきました。
関心をもつこと、知ることの大切さ。ダム建設管理の側からとの両方の見解が紹介されているのが良い。鎖川の上流を歩いてみたい。30年前、60年前の鎖川と現在があまりにも変わってしまった。10年20年と取り組み続けて、実現したこと。
川に入ろう、川遊びをして、川に近くなろうと盛り上がりました。
この映画で得られたことが多かったように感じましたし、そのような感想が参加者からも聞けました。


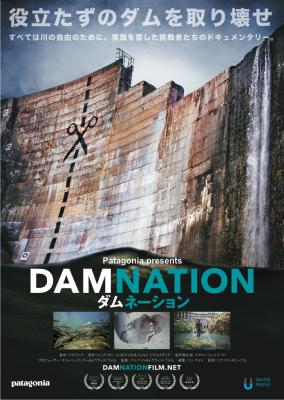
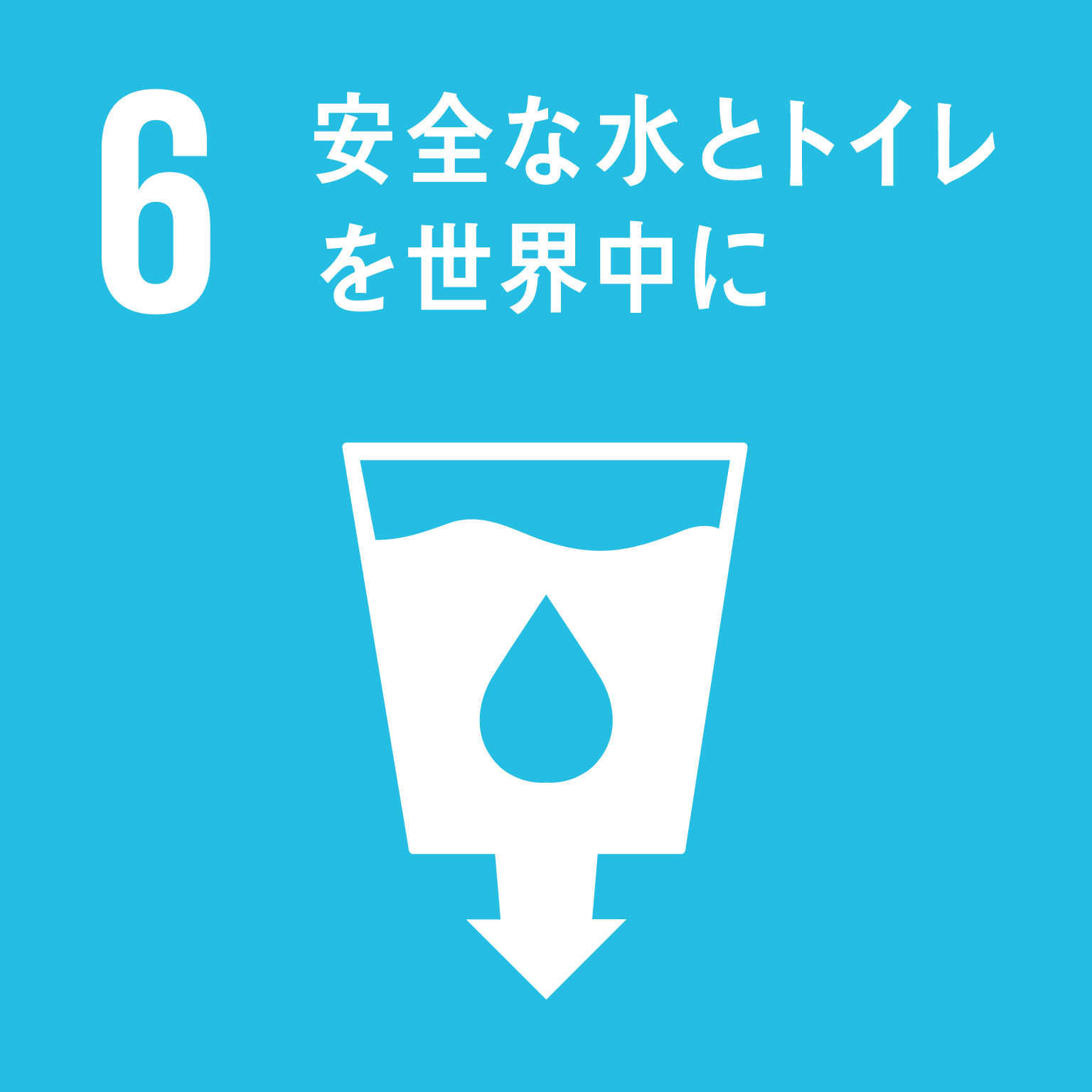
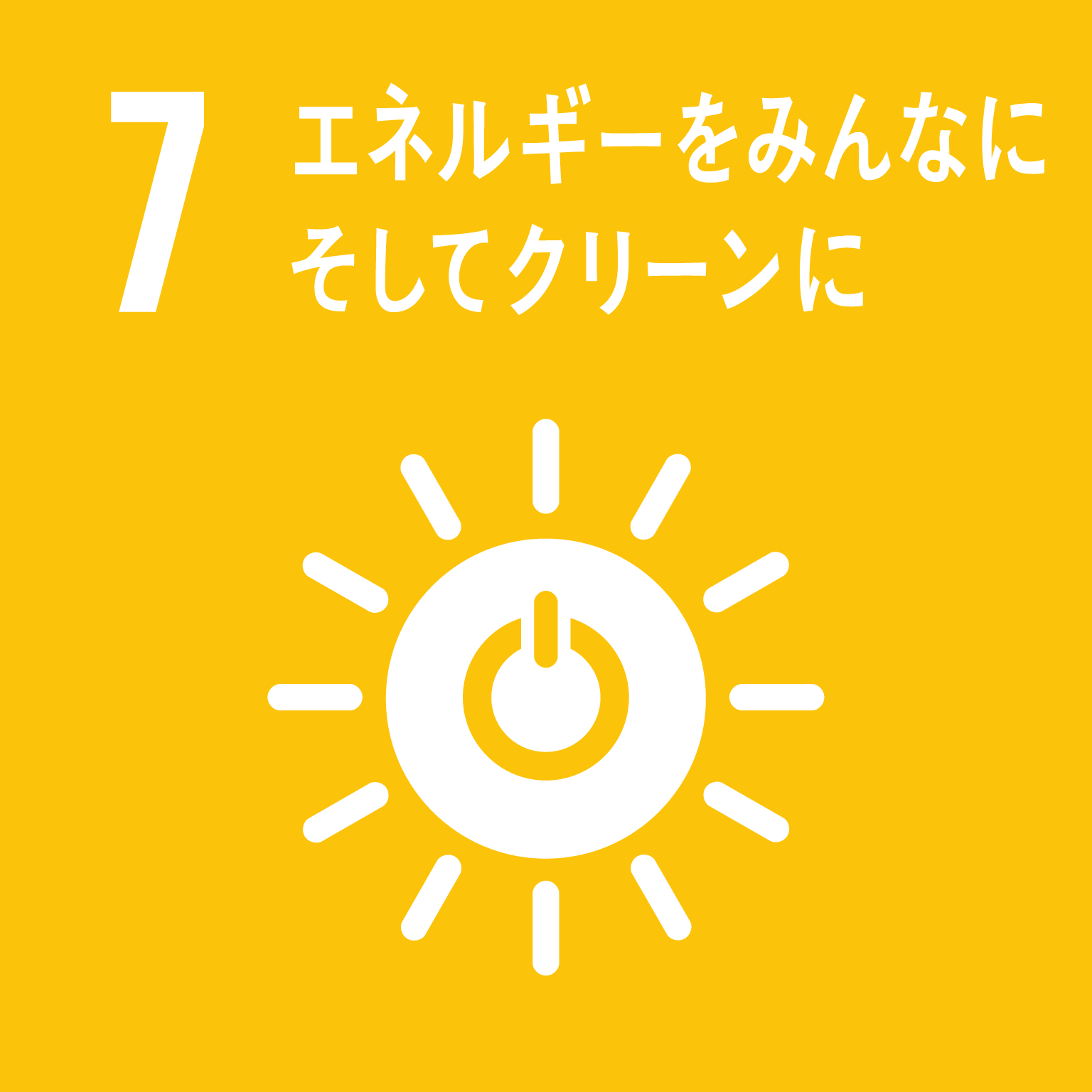


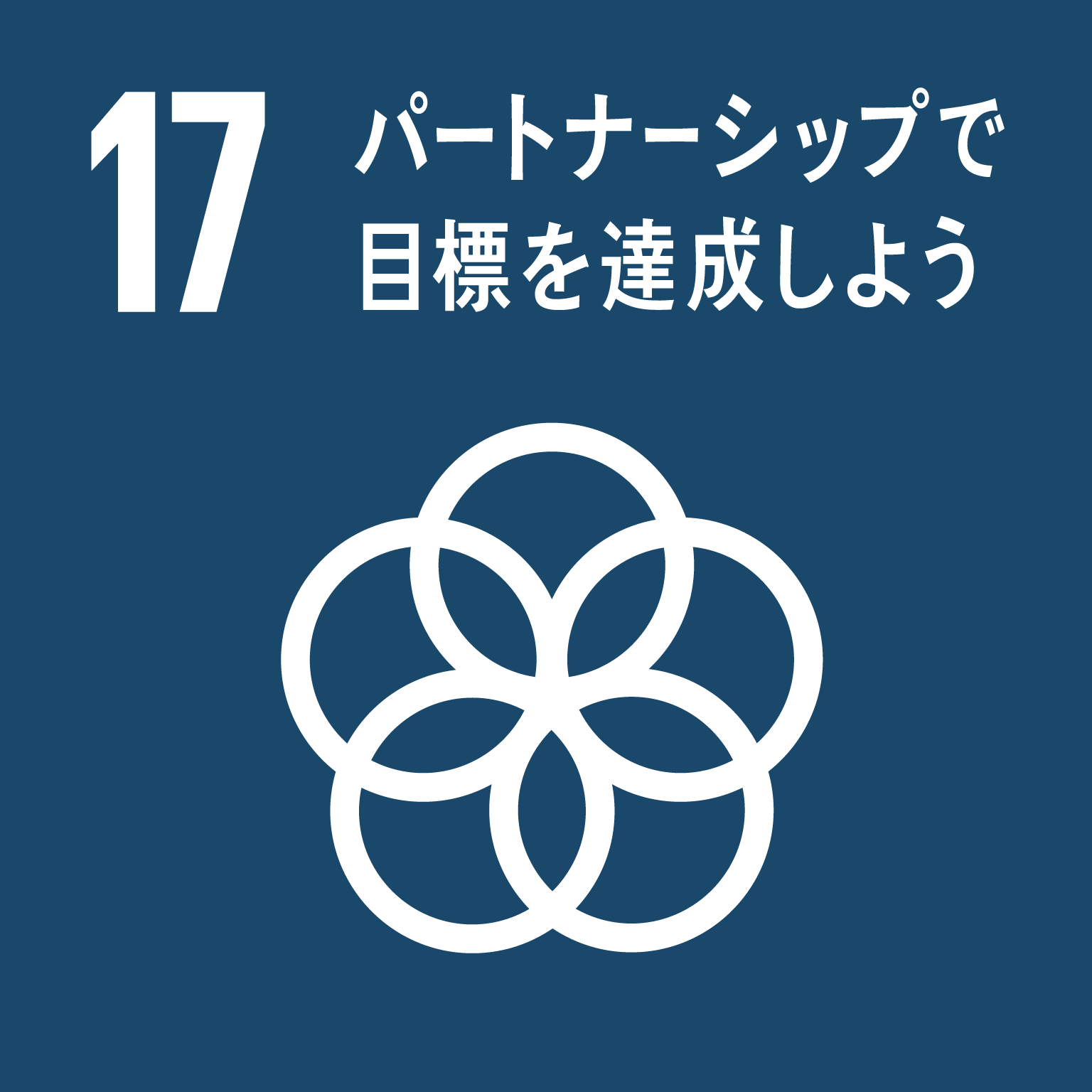


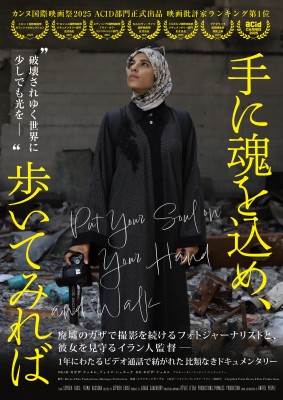

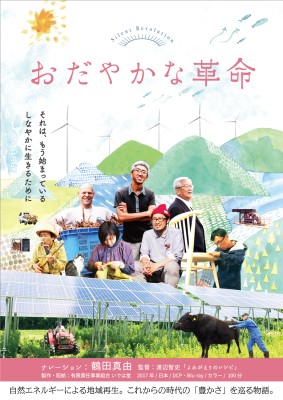




あるいは国の現状を憂いてそれを変革しようと小さな足掻きを営んでいる人々に、
必ず観てほしい映画である。
日本の環境運動に(或いは社会に)、決定的に欠如している
「とんちとユーモア」をまざまざと見せつけられる。
– 三宅洋平((仮)ALBATRUS/NAU代表)
***
今や諸悪の根源は、一人一人の小さな無責任。
今を生きる私達が気付き、動き出さなきゃならないんだ!
– 伊勢谷友介(俳優/映画監督/株式会社リバースプロジェクト代表)
***
この地球上に生命を授かった人間たち全てにこの映画を見て欲しい…!って思った。
山も川も海も美しく、そこに生きる生命の営みは
とてつもなく愛おしく美しいものなのだと、改めて考えさせてくれた。
この映画には、伏線で色んなメッセージが織り込まれていると気付かされる。
– 谷口けい(パタゴニア・アルパインクライミング・アンバサダー)
***
やっとダムは壊すものになった。原発もそうなる。
雇用はなくならない!どう自然に戻すか?
新たな知恵や技術が産まれ、未来に感謝されるクリエイティブな仕事になる。
日本もダムがない川がなくなって久しい。
八ッ場や最上小国川など未だ強引に汚い手段で無駄なダム計画が!
この映画を見て、アナタもNOと言って欲しい!
- 高坂勝(「たまにはTSUKIでも眺めましょ」オーナー/「減速して生きる―ダウンシフターズ」著者)
レビュー一覧
http://damnationfilm.net/message/