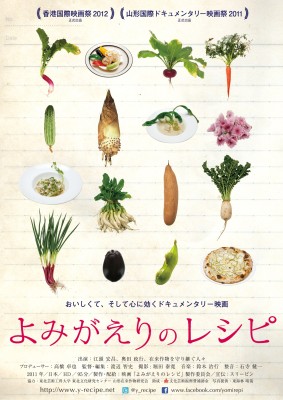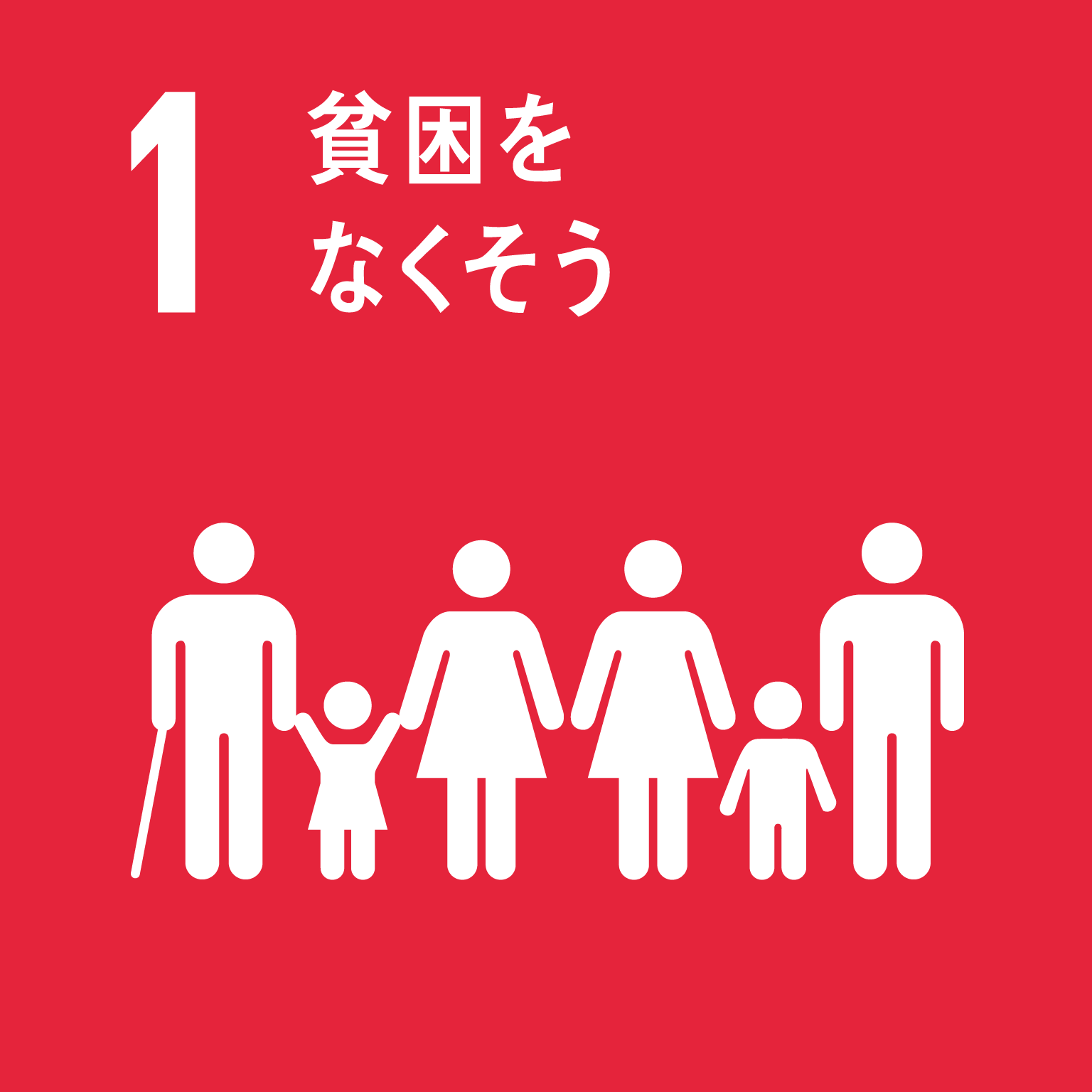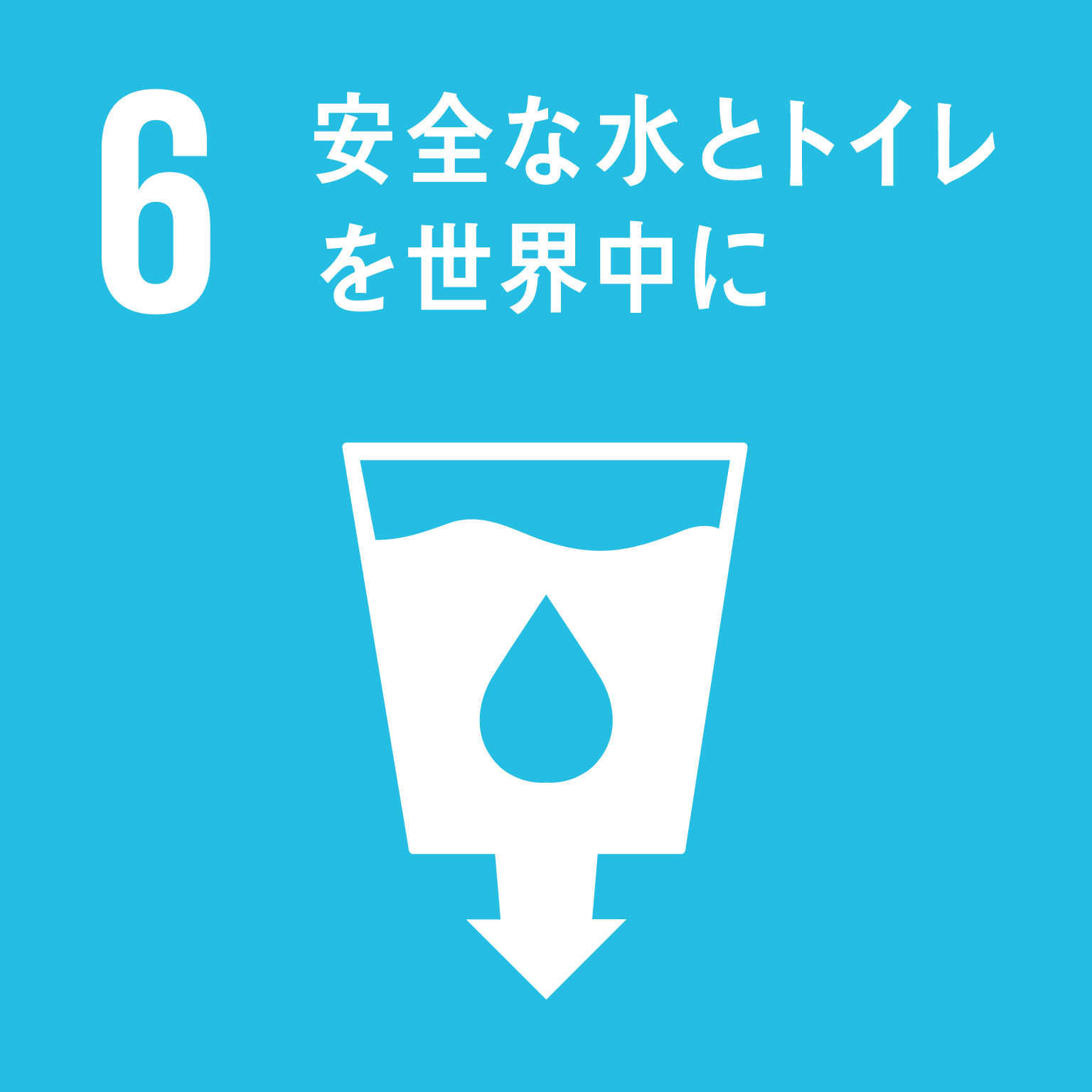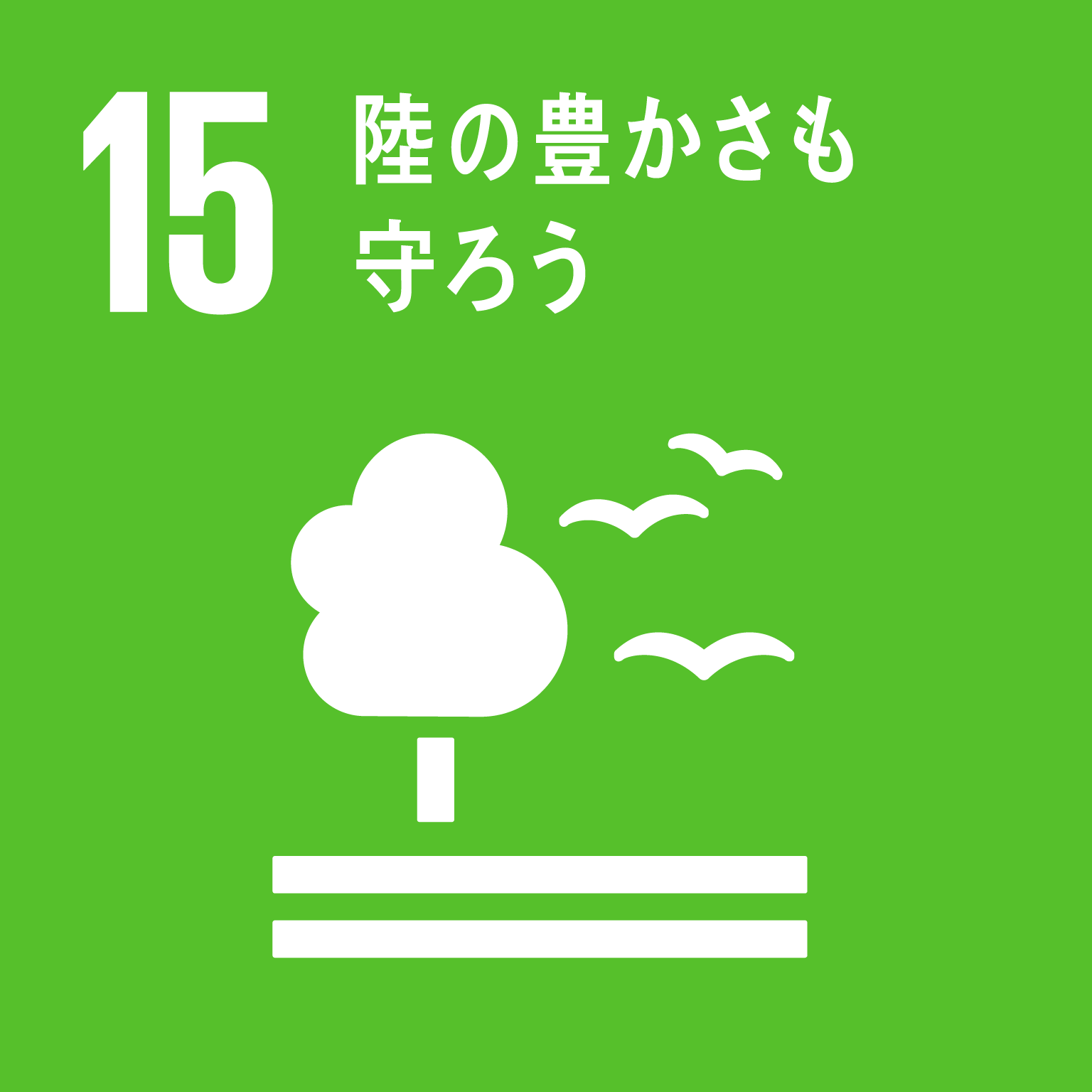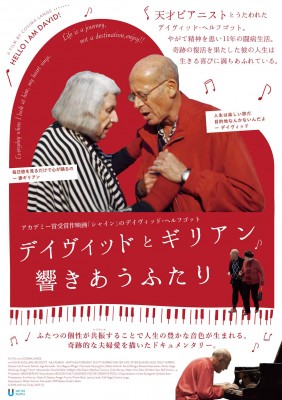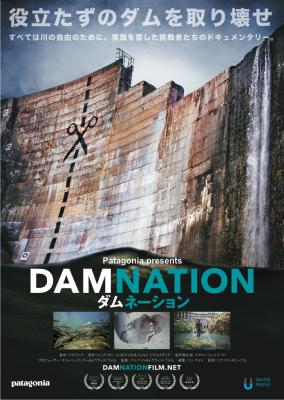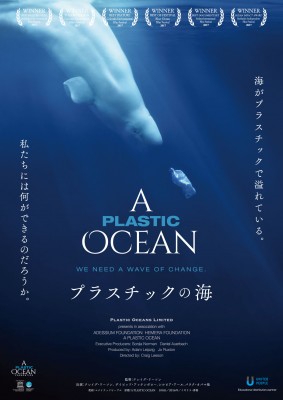2023ウナギネマvol.9『よみがえりのレシピ』
ローカルこそが時代の最先端。
鑑賞後に頭に浮かんだのは、これでした。
大量生産・大量消費の流れの中で、淘汰されていった在来作物。
価値観の多様化が、そんな作物に再び光を当てるようになりました。
驚いたのは、こどもたちが見事に風味の違いを味わい分けること。
誰から教わるのではなく、こどもたち自身が自分の感覚で「おいしい」と表現する。
昔からの生活や畑仕事を淡々とこなす農家の方々の姿。
その朴訥とも言える生き方が、在来作物を今に残してくれました。
これこそが文化の継承なのでしょう。
確かに、効率よく流通させるなど、社会の成長に合わせた改良も必要だったのかもしれません。
しかし、いつの間にか、本当に大切にしなくてはいけないものを忘れてしまっていたようです。
作物はモノではなく、すべて生き物だということ。
生き物である作物を、生き物として大切にすることで、私たち人間も生きていける。
作物の命は、私たち人間の命と深くつながっているのです。
作中に登場する「アル・ケッチャーノ」というレストランの料理が最高に素晴らしい。
シェフの奥田さんの、素材をとことん活かした調理方法が見事です。
ぜひ一度こちらのお店を訪ねてみたいものです。
次回のウナギネマは2/22(木)〜25(日)の4日間です。
上映作品は『グレート・グリーン・ウォール』。
マリ出身のミュージシャン、インナ・モジャが音楽で人々をつなぎ、壮大なアフリカン・ドリームの実現のため、気候変動の最前線へと旅する音楽ドキュメンタリー。
ぜひこちらの作品もお楽しみに。
 4/20(土)昼、第187回 銀座ソーシャル映画祭 x 第15回プロギング部ラン&ピースを開催しました。
4/20(土)昼、第187回 銀座ソーシャル映画祭 x 第15回プロギング部ラン&ピースを開催しました。