貧困援助がビッグ・ビジネスに?
あなたの”善意”が、誰かを傷つけているかもしれない
「この映画を観たら貧困と第三世界を決して同じ様に見れないだろう」
- マイケル・ムーア(映画監督)
News
- 2025/10/31
- 12月の寄付月間に映画『ポバティー・インク』上映しませんか?善意の裏に潜む問題とは
- 2019/10/15
- 12月「寄付月間」映画『ポバティー・インク~あなたの寄付の不都合な真実~』上映キャンペーン
- 2018/11/09
- 【12月は寄付月間】映画「ポバティー・インク~あなたの寄付の不都合な真実」上映キャンペーン!
- 2017/11/14
- 12月の寄付月間に映画『ポバティー・インク』を上映しませんか?
- 2017/02/11
- 映画『ポバティー・インク ~あなたの寄付の不都合な真実~』DVD予約発売中!

(c)PovertyCure
About the film
「貧しい気の毒な人たちのために手を差し伸べよう」「彼らは無力で何もできない」
そんなイメージを謳い、繰り広げられてきた営利目的の途上国開発は、今や数十億ドルに及ぶ巨大産業となっている。その多くの援助活動が失敗に終わり、援助の受け手がもともと持っている能力やパワーも損ないさえする。
私たちの「支援」がもたらす問題は?正しい支援のあり方とは?途上国とどう向き合うべきなのか?ハイチやアフリカを主な舞台に、“支援される側”の人たちの生の声を伝えるドキュメンタリー。
More info
営利目的の途上国開発業者や巨大なNGOなどにより、数十億ドルにも及ぶ「貧困産業」が生まれ、そのなかで先進国は途上国開発の指導者として地位を獲得してきた。慈善活動のビジネス化が歴史上これほどまでに発展を遂げたことはない。しかし、「気の毒な人々を何とかしなければ」「彼らは無力で何もできない」といったイメージを先進国側の人々に植え付けるプロモーションや、一方的な押し付けで受け手側の自活力を損なうような援助のやり方に、反対の声をあげる途上国側のリーダーは増えている。
本作『ポバティー・インク 〜あなたの寄付の不都合な真実』(原題:POVERTY, INC.)は、靴を一足購入するごとに途上国に一足贈るトムスシューズや、途上国発の太陽光パネルベンチャー企業、国際養子縁組やアメリカの農業補助金などについて取り上げながら、私たちに、支援のあり方について問いかける。20ヶ国で200人以上に行なったインタビューは、もはや無視することができない、“寄付の不都合な真実”を浮き彫りにする。
Data
| 原題 | POVERTY, INC. | 製作年 | 2014年 |
|---|---|---|---|
| 製作国 | アメリカ | 制作 | ポバティーキュア, アクションメディア コールドウォーター・メディア |
| 配給 | ユナイテッドピープル | 時間 | 91分 |
Cast & Staff
| 監督 | マイケル・マシスン・ミラー | 製作総指揮 | |
|---|---|---|---|
| プロデューサー | 原作 | ||
| 脚本 | 音楽 | ||
| 撮影 | 編集 | ||
| キャスト | ムハマド・ユヌス ジョージ・アイッティ ハーマン・チナリー=ヘッセ ポール・コリアー セオドア・ダルリンプル エルナンド・デ・ソト 他 | ||
Review(10)
今ではすっかり相対的貧困家庭に含まれる身には、貧困という言葉が持つ響きにある種の抵抗を感じます。貧しいから困るのではなく、困るのは、生きていくのが困難な社会の仕組みにあると感じているからです。映画の冒頭に「世界が変化しないのは、変化で損をするのは強者、つまり極一部の富者や権力者で、得するのが大多数の弱者だから」という内容のメッセージが流れ、寄付をはじめとした支援が今やpoverty inc.”貧困産業“として貧困を維持させている構図があることを指摘しています。
「貧しいから能力がない、力がないから貧しいのではない」。「必要なことは隔絶を無くすること」。映画のあらゆる場面で訴えられるメッセージに動揺しました。隔絶のひとつが、個々の中にも存在しているのではないでしょうか。これからの余生を貧乏神に取り憑かれている生きる凡夫にもまだまだできることがあると、なぜだか勇気が湧いてくる映画でもありました。人が生きる姿は本来とても美しい。鑑賞直後の今感じていることのひとつです。
17/03/27 15:11
17/03/27 15:14
17/03/27 15:18
善意の意味をもう一度考え直し、共に生きる方法を見つけられたらと思う。親を助けることで子どもたちを助けることができる。日本も同じことが言えるかと。
上映者の声
 6/15(土)昼、第192回銀座ソーシャル映画祭 x デモクラシーフェスティバル・ジャパンを開催、日本でも北欧のようなデモクラシーフェスティバルを進めているDemocracy Festival Japanと共催でした。
6/15(土)昼、第192回銀座ソーシャル映画祭 x デモクラシーフェスティバル・ジャパンを開催、日本でも北欧のようなデモクラシーフェスティバルを進めているDemocracy Festival Japanと共催でした。久しぶりの再上映作品、たぶん6回目の「ポバティー・インク あなたの寄付の不都合な真実」は、も古い作品ながら今でもお勧めできる秀作で、感想共有もいつも以上に活発でした。
今回は高校生のゲストスピーカーをお招きしましたが、これがまた素晴らしかったです。小学生でもフィリピンの体験から社会的課題に関心が高まり、中学生で国際ボランティアを学び、高校生になりケニア、ルアンダで活動。その考え方や行動力を、楽しく学ぶ機会となりました。
来週6/22(土)は、第193回銀座ソーシャル映画祭x第17回プロギング部ラン&ピースです。気軽にご参加ください。
申込は https://gsff193.peatix.com/ へどうぞ。


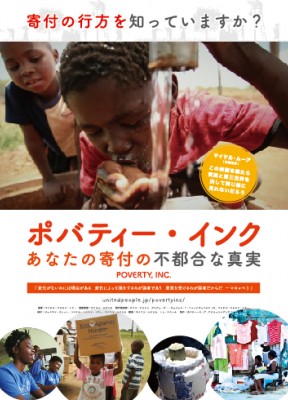
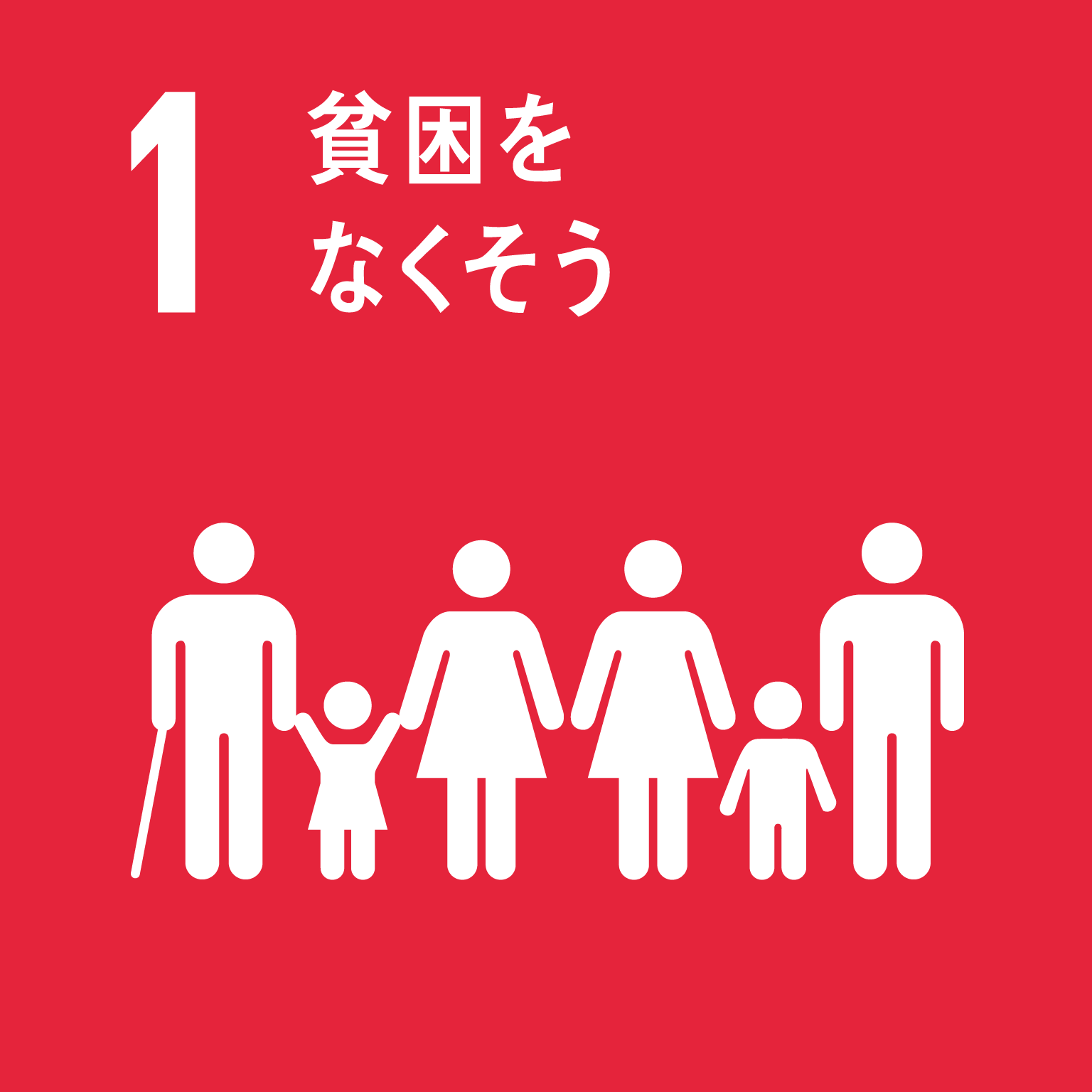

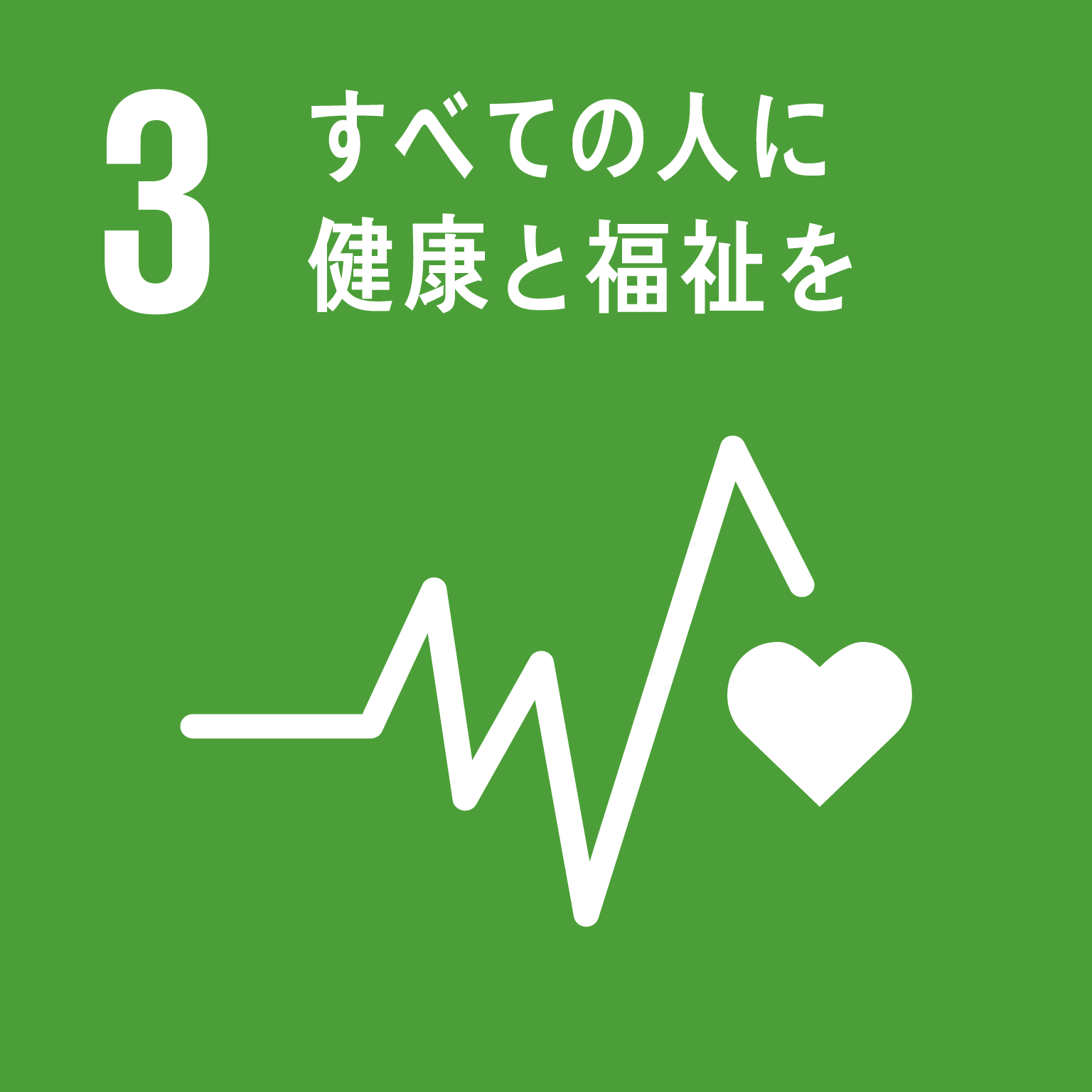
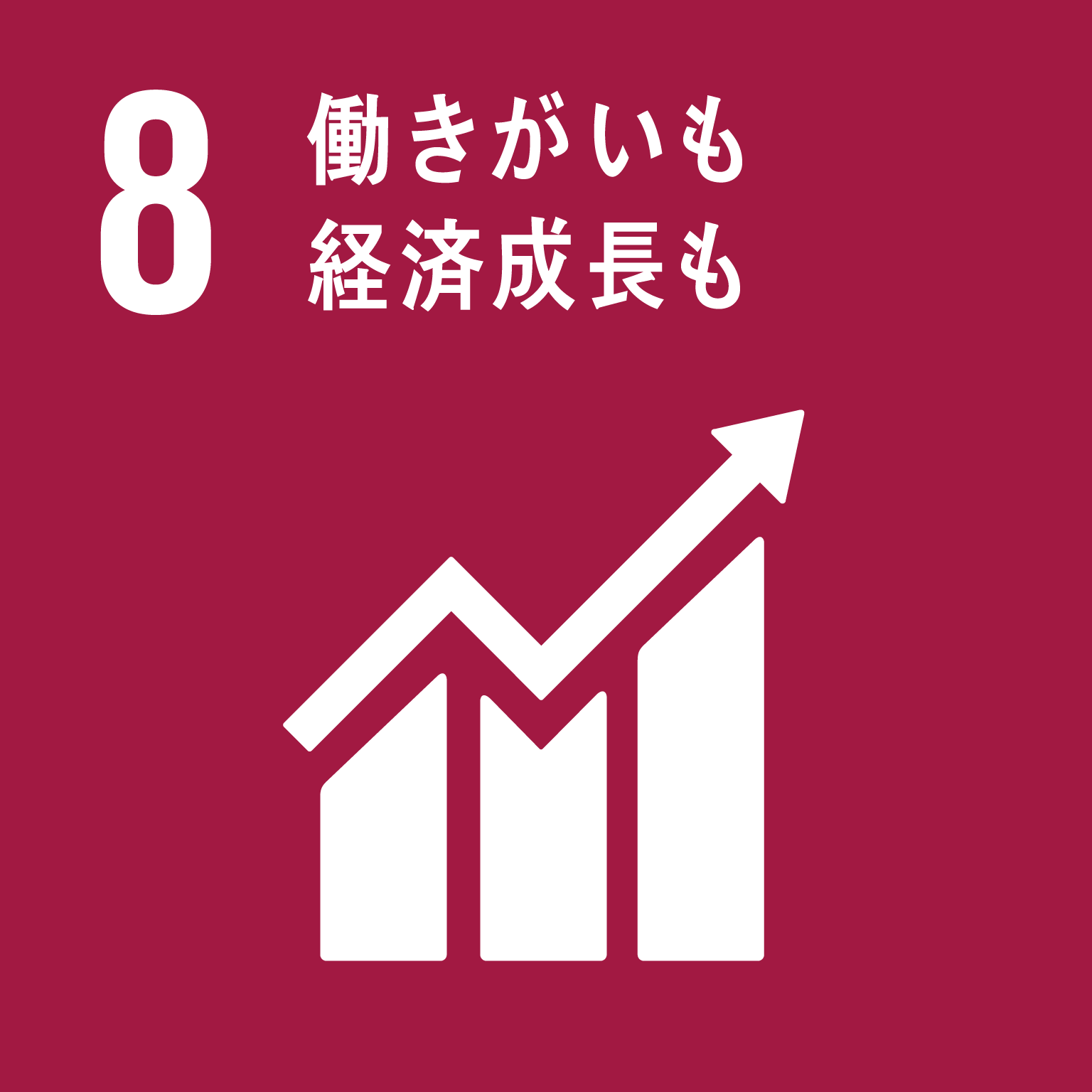
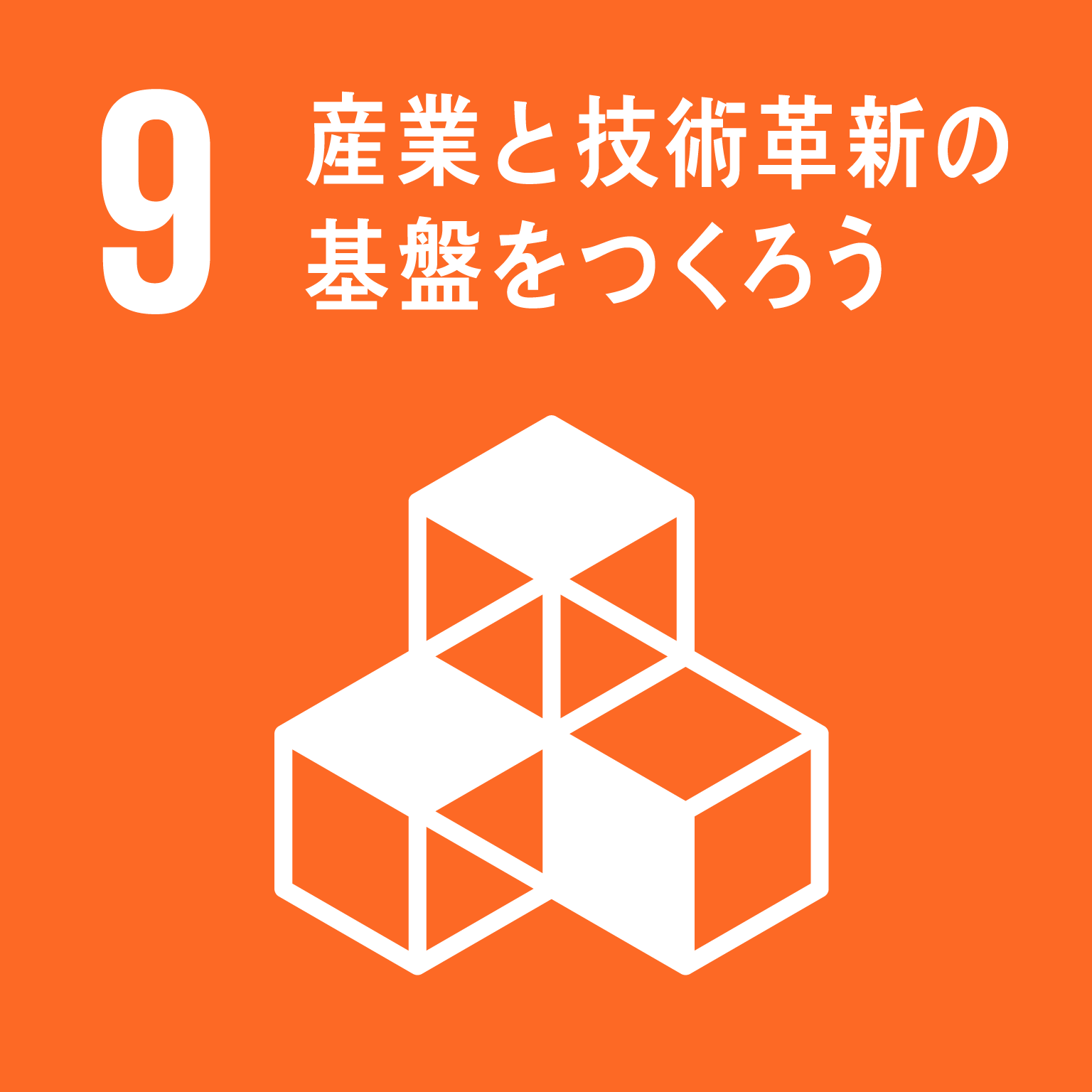
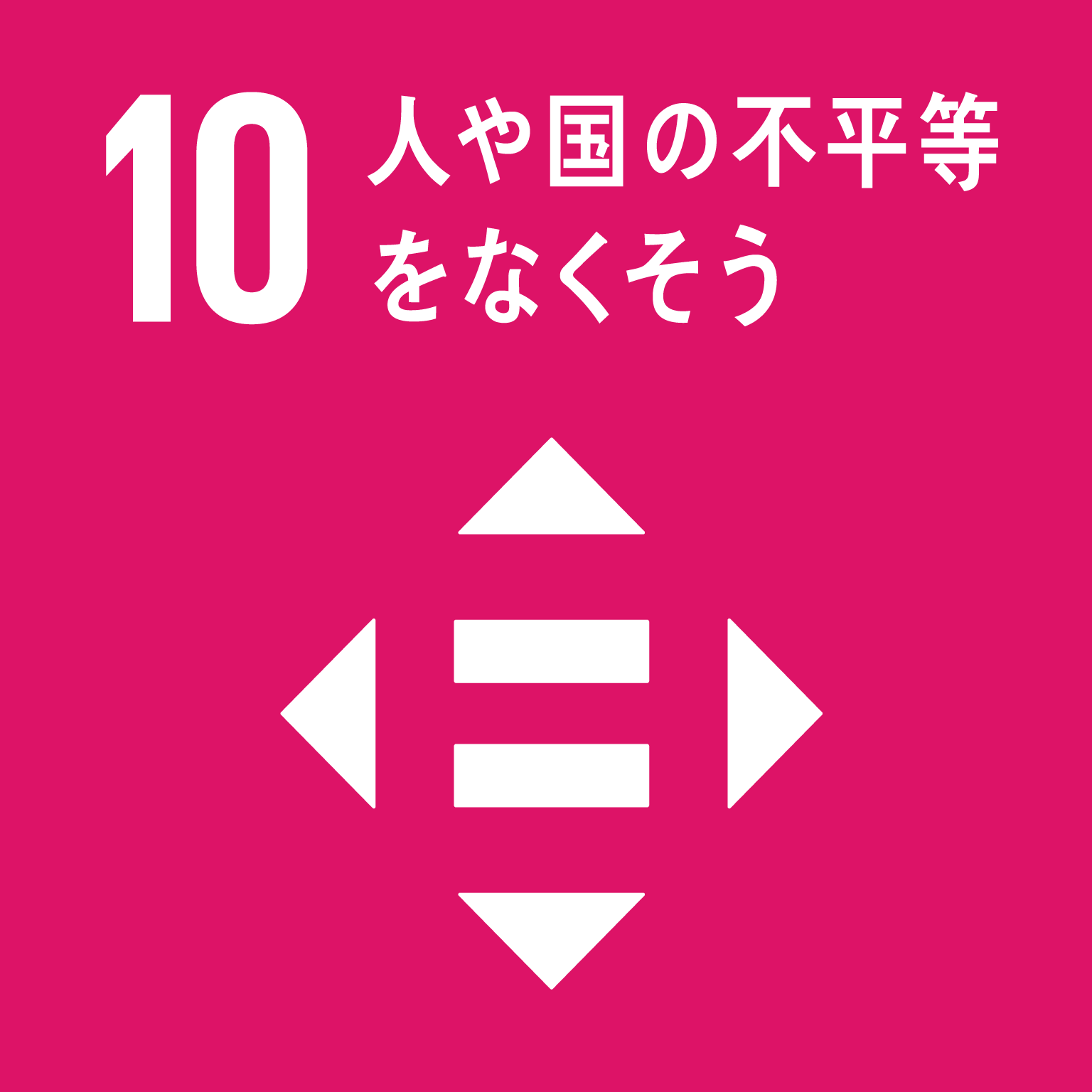


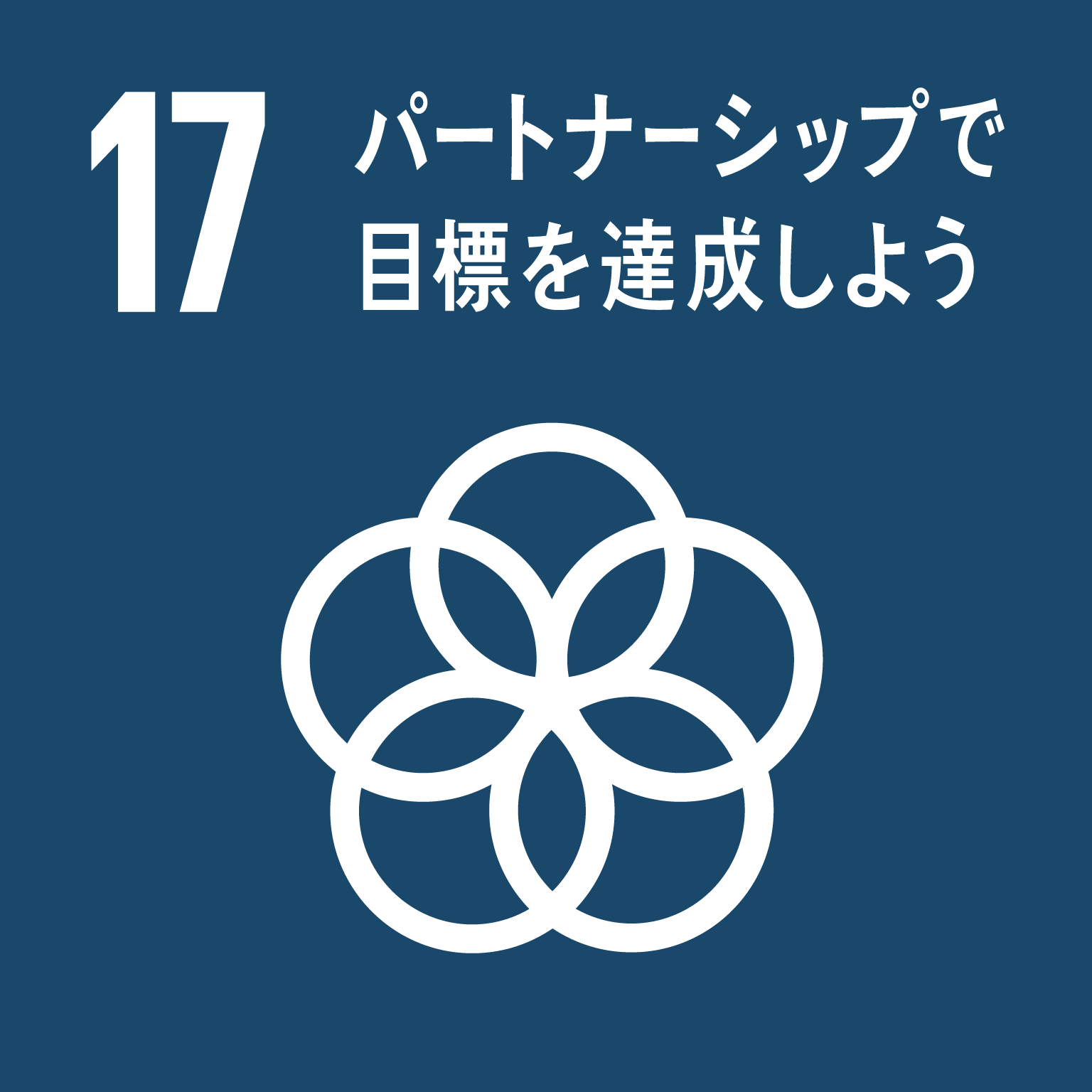
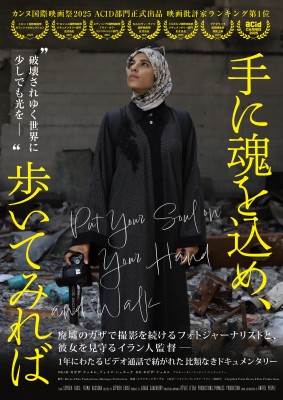
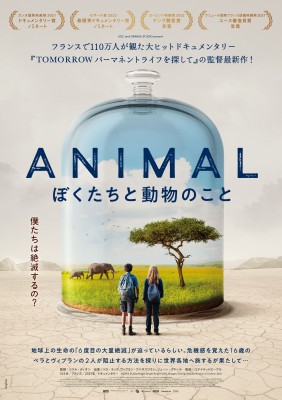
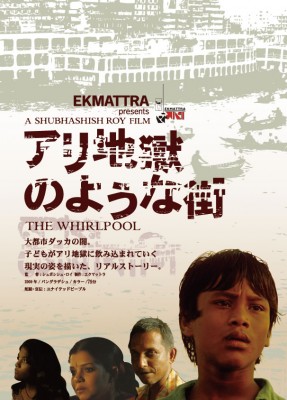

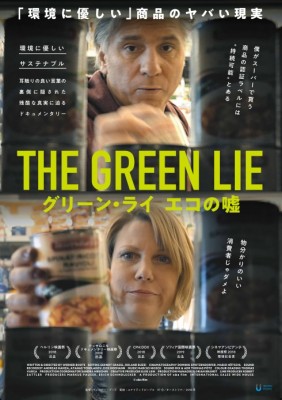





物心ついた頃から見聞きする「アフリカの飢える子どもたち」は、その数の多さからにしても、いつになったら解決するのだろうとどこかで思っていた。
私たちは目の前の現象に、即座に反応してはいけない、心動かされることがあったとしても、一旦その感情を置いて、トヨタ式ではないけれど「なぜそうなっているのか」を幾度も問い、コトの全体観を掴むべきなのだと強く感じた。
そしてもうひとつ、「支援」や「サポート」というのは、その対象に寄り添うものであり、支援する側の独りよがりな提供であってはならない。余計過ぎるお節介は、時に相手から生きる力さえも奪うことがあるということ。
寄付の話だけど、きっと寄付の話だけでなく社会のどこかにこの不都合はたくさん横たわっている。私たちは、それらをどう知り、どう行動すれば、不都合な真実を変えていけるのか・・・。この確信的で世界的な構造は根深い。