「修理したいのはモノだけじゃなかった。」
オランダ発祥リペアカフェに集う、人とモノを巡る物語。
About the film
お店では修理を受け付けてくれない壊れた家電や服、自転車など、
あらゆるものを地域のボランティアが無料で直してくれる、オランダ発祥のリペアカフェ。実は彼らの役目は、モノを修理するだけではない。
離れ離れになった家族の「思い出」、疎遠になりつつある地域の「コミュニティ」、捨てることを前提に成り立つ消費社会の「システム」…
リペアカフェにはどのような人とモノが集うのか?壊れかけた「モノ以上のもの」を直す人々の物語がここにある。
More info
あなたの周りに眠っている、壊れたままのものはありますか?
ほつれたニット服、ひび割れたタブレット、小さい頃に遊んだおもちゃ……それぞれに思い出やストーリーがあるでしょう。
しかし、大量生産・大量消費が前提となる社会では、私たちは、気付けばモノが壊れたら新しいものに買い替えるのが当たり前になっています。お店で修理を頼むよりも新品を買う方が安かったり、自分で修理するのが難しかったりすることもあります。
そんな壊れた家電や服、自転車など、あらゆるものを地域のボランティアが無料で直してくれる場所があります。その名もRepair Cafe(リペアカフェ)。
IDEAS FOR GOODが贈る、初のオリジナルショートドキュメンタリー『リペアカフェ』は、そんなリペアカフェ発祥の地であるオランダ・アムステルダムを舞台に、彼らの活動に密着。その中で生まれたコミュニケーションから、私たちの身の回りにあるモノと人との関係性や、真の豊かさを見つめ直します。
2024年7月、欧州では消費者が製品の修理を簡単にするために「製品の修理を促進する共通指令」が施行されました。これによって、テレビ、掃除機、携帯電話など11種類の家電について、購入から最大10年間、メーカーが修理サービスの提供を行うこと等が義務付けられました。
製品の設計段階からごみが出ることを防ぎ、資源を高い価値を保ったまま循環させ、自然を再生していくことを目指す、サーキュラーエコノミー。こうしたシステムを推進する上で、最小限のエネルギーで製品の寿命を伸ばす「リペア」は重要な鍵となります。
日本でも、2024年7月にサーキュラーエコノミーに関する関係閣僚会議が開かれ、リペアを通じた地域活性化やライフスタイル転換の必要性が議論されています。
地球の健康状態を示すプラネタリーバウンダリーが限界を迎えつつある現在。これからもこの地球で幸せに暮らし続けるために、「修復」や「再生」を通じて、どうすれば豊かな社会を築き、ともに生きていくことができるでしょうか。
今こそリペアを通して、モノと人の関係性や、真の豊かさについて見つめ直してみませんか?
Data
| 原題 |
The Repair Cafe |
製作年 |
2024年 |
| 製作国 |
オランダ、日本 |
制作 |
IDEAS FOR GOOD 協力:Repair Café International |
| 配給 |
ユナイテッドピープル |
時間 |
30分 |
Cast & Staff
| 監督 |
瀬沢正人 |
製作総指揮 |
|
| プロデューサー |
|
原作 |
|
| 脚本 |
|
音楽 |
|
| 撮影 |
瀬沢正人 撮影応援:龍ノ口弘陽 |
編集 |
瀬沢正人 |
| キャスト |
|
上映者の声
上映会を主催された方の声を紹介します
「リペアカフェ」の上映と併せて、ダーニング体験を実施しました。
30分の映画とのことで、体験型のワークショップを一緒に企画しやすい作品でした。
内容は、30分のなかで、個々人の暮らしからコミュニティ、そして社会的な問題提起まで、理解しやすく伝えてくれるあたたかな雰囲気のものでした。
この映画のおかげか、またこの映画に集まってくださった方々のおかげか、その後の体験では参加者同士のコミュニケーションも多く、上映会場をすてきなリペアカフェにできたのではないかと思います。
参加者の方々からは、今後もリペアカフェを開催してほしいという声や具体的なリペアしたいもののアイデアがたくさん挙がりました。この上映会をきっかけに、リペアカフェ企画を続けてみたいと思っています。
リペアカフェの上映と共に、上映地の小布施町でリペアをしている方々の紹介や品物の展示をしました。
上映前と上映後に監督の想いを語る映像を皆さんに観てもらい参加者と思いを共有したと感じています。
小布施町でも
・リペアカフェをやりたい。
・リペアカフェがあったら参加したい。
・物を消費し続けることはこれからの時代にはあわない。
・人とつな がり物ともつながることを大切にしていく文化を
取り戻したい。
などの感想が聞かれ、豊かな上映会になりました。
ありがとうございました。
今回は上映会の後に、古着のリメイクワークショップも合わせて行いました。
映画ではリペアを通じた人との繋がりやコミュニティが生まれる様子が映されていましたが、映画をきっかけに、我々の上映会&ワークショップでも同じような繋がりが生まれたのではないかと思います。
知らない人同士でもそれぞれに映画の感想を言い合い、手を動かしながら同じ空間を共有することで、まさにリペアカフェのような温かい時間を過ごすことができました。
巡る暮らしのおすそわけ&リペアカフェ上映を開催して
パーマカルチャーデイのイベントとして、リペアカフェを観てシェア会をして、実施に繕いたいものを持ち寄ってダーニング(繕い)をしました。映画は30分と短いながらもとても味わい深く、シェア会では実際に今後リペアカフェをやりますという声も。
ただモノを直すだけではなく、人のつながりやモノとの関わり、価値観を見直すような場がリペアカフェなんだと感じる映画でした。もしリペアカフェをやるなら?には沢山のアイデアが出ました。
その他にも、一品持ち寄りのポットラックランチ、金継ぎの紹介。共感サークルやギフト交換など、リペアとおすそわけの豊かな時間になりました。

■30分のドキュメンタリー映画でこれほどまで涙が出るとは思いませんでした。
ただのリペア(物を直す)だけではない、直るのは、物だけではない。直す人も、直してもらう人も、みんな温かい気持ちになって、次の自分が取るべき行動を考えるきっかけになっている。そして、たとえ直らなくても、そこに学びがあって、次の自分が取るべき行動を考えるきっかけになっている。とてもいい映画でした。
■リサイクル、リフォーム、リメイクとリペアの境界に、繋がりの意が強く認識されている事が大きな気づきとなりました。
家族、親戚、ご近所さん、友人、知人など、日常の暮らしは当たり前にお互いに支え合って来た世代に、再生、再利用のシェアは普通の感覚でしたが、今、これからは敢えてでも、更に地球レベルの環境への気配りが個々人に必須、と周りの人々ともち認識とアクションを共有していこうと、改めて腑に落としました。



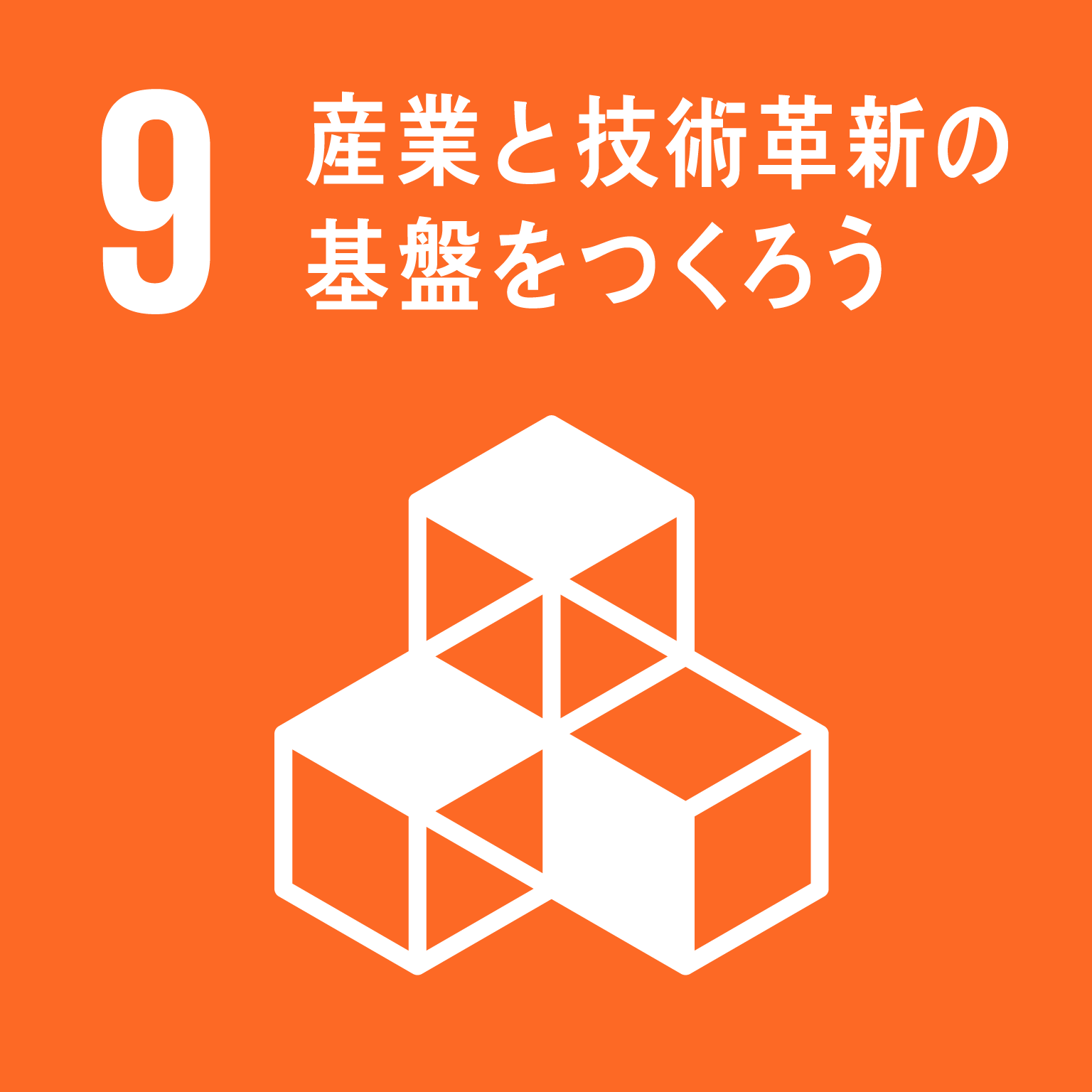


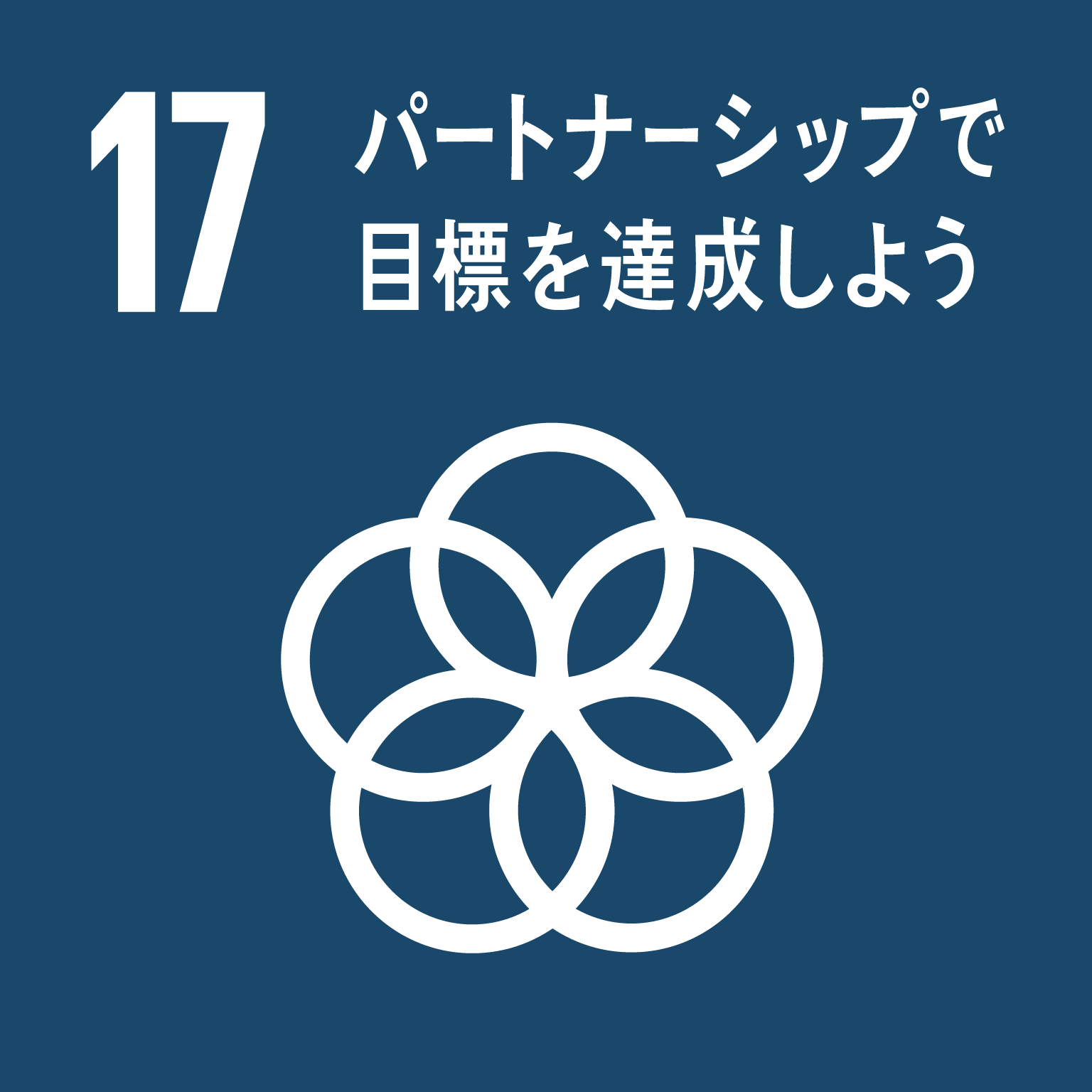
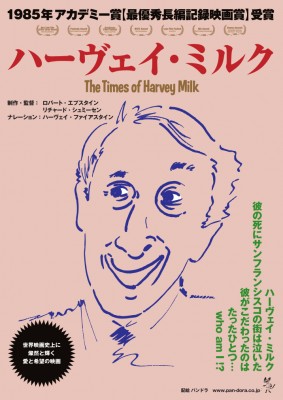

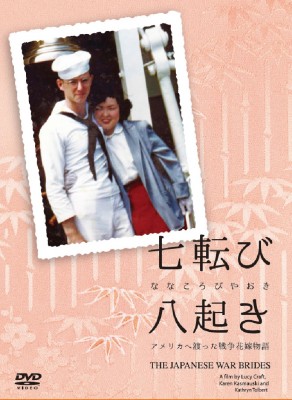




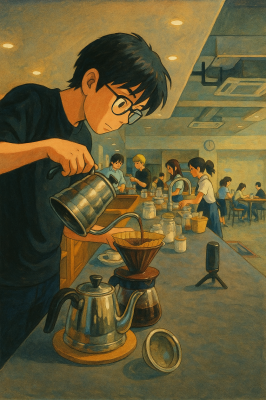


映画の中身は、修理市場みたいなところに集まって、知っている人も見知らぬ人も、思い入れのある道具や服や機械を直して、笑顔になっていく。時には直せない。直せるようには作られていないものが多い。私も昨日バリカンが壊れたので直そうとしたら、部品そのものが腐るようにできてて、直らない。バッテリーも元気なのに、綺麗なのに直せない。なんだか「もったいない」し、心がなんとなく「寂しい」。
修理人と呼ばれる人々が楽しそうだ。みんなの寂しいに寄り添い、解決してくれる。早速、似たようなものができないか、考えてみたい。そう、自分の街だってリペアしちゃおう。これまでCinemoで17回上映してきたけれど、一番良かったかもしれない。